これまでのコラムが納めてあります。
※バックナンバーはNO.1~NO54です。できれば、通してお読みください。
(根底に流れるものを、くみ取っていただけると思います)
![]()
![]()
![]()
![]()
これまでのコラムが納めてあります。
※バックナンバーはNO.1~NO54です。できれば、通してお読みください。
(根底に流れるものを、くみ取っていただけると思います)
院庄地区観月会 一月三舟(月のお話) だんじり(岡山市) 院庄地区文化祭
NO.54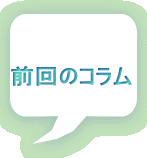


小雪を過ぎました。じっくりと秋を味わう間もなく、冬が来たような感じです。それでも、例年よりは高い気温だそうですが、酷い夏のダメージを受けた体には厳しい寒さのように感じます。 テレビ(もっぱらワイドショー)では、斎藤知事が当選した兵庫県知事選挙に絡んで、SNSのあり方や関わり方が喧しく議論されています。所謂、斎藤知事当選に貢献したといわれる人が自身のアピールとしてSNSに「やったこと」を挙げたことが発端のようです。公職選挙法上からは、色々と問題があるようですが、一方で選挙へのSNSの影響に関するルールについては確立したものが無いようです。 そもそも、急激な進化をとげるICT分野に対して、従来からある法律などが適応できないことが考えられます。また、様々な分野においてAIが活用され、そのことによる新たな問題が次々に出てくる状況の中では、夫々の分野を踏まえたSNS活用に関するルール作りも間に合わないのかもしれません。いずれにしても、アメリカ大統領選挙等を見ていると何を信じたらよいのか解らないという感じでした。 さらには、ユーチューブをはじめとしてこの分野が安易にお金を稼げるという側面もあります。とにかく発信してしまえ~という風潮が高まり、高い倫理観に裏付けられた判断などというもものは見過ごされがちです。その背景に、先ず訴えてから相手の出方を見る~というような欧米式、或いは中国的な手法を感じてしまうのは、日本人の精神性などという考え方に立つ私が古いのかもしれません。 もちろん、このような文章を作成したりするときにおいて、WEB上を通じて情報を手軽に入手できるという意味では、インターネットは大変便利です。しかし、例えばその匿名性をとっても非常に危険な部分があります。その典型的な例が、闇バイトなどという犯罪行為への誘惑です。バイトなどといえば、何か罪が軽くなるようなイメージが湧くのかもしれませんが、強盗致傷などというと大変重い罪になります。 結果的に、長期にわたる懲役刑に処せられる場合もあります。けっして、バイトで済まされることではありません。さらにいえば、ブラックとかホワイトとかいう言葉でごまかせることでもありません。大体我が国においては、時代と共に言葉が軽くなるような気がします。指摘しておきますが、援助交際は売春ですし、パパ活なども同義語だと思います。どのように言葉を変えても、罪は罪犯罪は犯罪なのです。 とはいえ、この分野を利用して世論への影響を図る行為や、都合の悪い情報を遮断するような動きは、既に国家的な規模で行われています。この点に関しても、我が国は寛容すぎると思いますし、対策が遅れていると言わざるを得ません。本来は、嘘をついたりデマを流すことの方が悪いのですが、ネット社会では行ったもの勝ちのようなところがあります。また、責任追及もし辛いのが現状です。 少し話がそれますが、嘘をつく人間はどこまでも嘘をつくものです。それは、その嘘を正統化するために、嘘をつき続けなければならないからです。また、そのような人間に限って、過去の発言等には知らん顔です。自身の変節にはお構いなしに、他者の発言にけちをつけ姿勢をあげつらうことに終始するばかりです。まことに、厚顔無恥とiいうところですが、それで良いと思うのがそういう人達です。 私も、色々な被害を受け対峙する場面もありましたが、基本的には話すだけ無駄です。そもそも私は、人間として認められないような相手とは話したくない性分ですが、立場上或いは職業上相手をしなければならないこともあります。そのようなときは、同じ土俵で議論などしたくないので極めて不快です。しかし、この頃思うことは、そうした「言わずもがな」を改めて言うべき場面もあるのかなぁと言いうことです。 言い換えれば、まぁ良いかな~などと言っているうちに、当たり前のことがどんどん当たり前でなくなるということなのかもしれません。ちゃんとした人は解っているはず、などと思っているうちに、どんどん嘘やデマが浸透していくのが今の世の中かもしれません。どんな時にも、明確な主義主張を唱えていなければならないのかもしれません。それが、一億総SNS社会で生きる術ともいえるでしょうか。 しかし私は、そのようなことにどうしても馴染めない気がします。だからという訳ではありませんが、X(ツイッター)やフェイスブックなど所謂SNSによる発信はしていません。頻繁に自らを露出する行為は、単に恥ずかしいという気持ちもありますが、一方でそこにどうしても見られることを意識した自分とは違う自分ができてしまいそうな気がしてしまいます。それが怖いのです。 とはいえ、例えぼやきとしてでも語りたいことはありますので、このような場に思いを綴っています。できれば、わざわざお尋ねいただき私の思いの一端に触れていただければ幸いです。
11月半ばとなりました。立冬も過ぎ、本来なら「秋深し~」という気分に浸りたいところですが、どうもそうはいかないようです。何というのか、肌感覚と暦があわないことに慣れていく自分が怖くなります。
怖いといえば、「もしトラ」から「またトラ」が現実になったアメリカ大統領選挙の結果です。そもそも、私などは選挙の経緯(行われている実態)を見ていて、これでよいのかななどと思ってしまいます。相手をののしり合い(程度の差は別として)、実現可能なことも不可能なことも、有権者の耳に優しいような言葉を振りまきながら、自身の優位性をアピールしていく選挙のあり方に強い違和感を覚えました。 また、その背景にある二大政党制というやり方にも首を傾げたくなります。あのようなやり方で、本当に民意は反映されるのでしょうか。とはいえ、専制国家であれ民主主義国家であれ、1人の代表を選びその人の判断により、多くのことを決めていくことに変わりはありません。決定的な違いは、国民がだめだと思った時に直ぐに変えられるかどうかということだと思います。 しかしながら、今回のアメリカ大統領選挙の様子を見ていて感じたのは、変えるための選択肢が果たして十分と言えるのかということです。もちろん、アメリカには下院・上院という議会もあります。また、大統領を取り巻くブレーンも優秀な人材が多くいるはずです。とはいえ、大統領の権限は強大であり、自分の意に沿わない人を粛清し、自らに都合の良いキャビネットを作ることは容易なことでもあります。 既に、遺恨に基づくものでは無いかというような人事の動きも伝えられています。今後、我が国を含めた国際社会に対し、恐ろしい影響が出ないことを願うばかりです。そして、もう一つ気になるのは自国第一主義的な内向きな考え方が拡がり続けていることです。例えば、かつてアメリカが国際社会において強い影響力を持っていた頃は、物品両面において世界の警察官的に動いていたからだと思います。 そもそも、新たに就任される大統領のように「アメリカファースト」といった時点で、分断と格差社会を助長するということになります。また、アメリカがナンバーワンであるためには、国際社会においてそれなりの責任を果たす必要があるということです。貿易においては関税を押し付け、同盟国に対して防衛費の負担増を求めておいて、得られる果実のみをアメリカのみが享受するという理屈は通りません。 実際には、国際経済は複雑で、それ程簡単ではありません。需要と供給、或いは生産するものと消費するものが必要なわけですから、一国がその富を独占するというのは難しいことです。さらに、そこには貴重な天然資源のようにサプライチェーンの問題もあり、売る側と買う側による経済力のバランスの問題なども考えられます。言葉でいう程、簡単に解決する問題ではありません。 一方で、地球のキャパも限られています。掘って掘って掘りまくれという風に、化石燃料を掘りまくれば、受容を超えた環境への悪影響が出ることは誰が考えても明らかなことです。結果的に、コントロールできないような猛暑や豪雨など、異常気象などが多発することにより多くの人が棲家を失い、生きていくのもままならないような状況になることさえ考えられます。 そんな状況下において、もはや存在意義を失った札束(電子マネー)を数えているような光景は、虚しいというよりは空恐ろしいものだと言えます。前回は、民主主義の実践について述べました。しかし、本当は民主主義の危機についても言及したいところです。私達は、本当に身の回りの小さなことから、きちんとチェックしていかなけれななりません。それは、本当に面倒くさいことに違いありません。 言い換えれば、本来は、日本人の精神性ともいえる常識の範囲であったことかもしれません。改めて口にしなくても、そんなことをして良い筈がないというようなことが、ケロッとしって行われるような風潮は高まり続けています。また、そのよう厚顔無恥な人間も増えていると思います。そのような人たちが、嘘やデマを繰り返し本当にしてしまう恐ろしさを、メディアや世論が払拭していく必要があります。 例えば、かつてのこの国の人々の考え方の根底にあった日本人の精神性に根差せば、そうした人たちは極めて少数でありました。また、そのような人間はひそひそと陰で蠢いていたはずです。ところが今日、そのように影で作り上げて来た悪意や独善的な振舞が、突如(ではないのですが)表通りを闊歩するようなことが起こっています。それは、身近なところから国際社会まで多様な場に現れます。 そのことを、チェックしていくことは本当に大切なことです。そして、それは「頑張ってね」ではいけないといいうことです。私も、よくその言葉を耳にしますが、私も頑張る、或いは一緒に頑張りましょうでなければ、本当の民主主義は実現できないのだと思います。
10月最終週です。日差しの強い日もありますが、肌に感じられる風は大分冷たくなってきました。少しずつですが、秋は深まっていきます。 その、冷たくなった秋風が身に沁みるのは、やはり与党である自民党・公明党なのでしょうか。衆議院選挙の結果は、厳しいものになったようです。結果的に、裏金問題や不透明な政治資金の扱いに関して、自民党政権に奢りがあったことについて、国民の厳しい審判が下ったと言わざるを得ないのだと思います。やはり、多数を占めた政権が長く続く時、どうしても政治は澱みがちです。 一方で、民主主義の政治の良いところは、その政権が悪かったら変えることができるというところです。実際、国民の支持が得られなければ、政権を手放さなければない訳です。私は、この点が現在我が国を取り巻く専制国家との、大きな違いだと思います。その上で、スーパーチューズデーまであと少しとなったアメリカ大統領選挙についても、強い関心と懸念が寄せられるところです。 そもそも、選挙そのものが劇場的なアピール合戦になっていることが、どうしても私には馴染めず納得できないところです。そのようなやり方が、うそだろうが何だろうが相手にダメージを与えれば良いとか、実現できようができまいが有権者に受けることを言えばよいというような状況に感じられます。まことに、支離滅裂な選挙を、多額な費用をかけて行っているという風にしか見えないのです。 一時は、グローバリズムによる経済発展が叫ばれ、世界中でその成果が謳歌されていたはずですが、共通の物差しでないやり方が歪を生まない訳がありません。もとより、経済とイデオロギーのダブルスタンダードが矛盾しない筈もありません。さらには、そこには宗教や民族問題など、多くの人間の情緒面に由来する確執もあります。このことは、長い歴史を経ても解決せず今日に至っています。 そうしたことを背景に、お金がすべて~というような我先の経済活動の成果がもてはやされ、格差社会は急速に拡大し続けています。結果的に、そこから取り残されていく人々の不満は、マグマのように溜まっていきます。時として、人々の関心は手っ取り早い解決策の模索に走り勝ちです。そのことが、ドメスティックな自国第一主義につながっていくことは、誰もが容易に想像できることではないでしょうか。 例えば、現在アメリカで行われている狂乱的な選挙の状況は、そうした世界的な人々の不満や不安が投影されているともいえるでしょう。しかしながら、一時の苦しみから逃れるために、或いは目先の利益のために誰か一人の独裁者を望むような考え方が、人類の歴史に多くの悲劇をもたらしてきたことにも目を向ける必要があります。また、私達はそのことを忘れてはならないはずです。 他方、ロシアのウクライナ進攻やイスラエルによるパレスチナ攻撃は、収拾する糸口さえ見えません。例えどこか(一部)に正しいもの(正義)があったとしても、正義の戦争などがあるはずはありません。また、あってはならないものだと思います。今すぐ、無益な戦いを止めるべきです。もう少し言えば、現在広まりつつある自国第一主義的な考え方は、そのような危険を多分に孕んでいます。 一例ですが、ハンガリーのオルバン政権によるマスコミに対する統制や、それらのことを都合良く使い自国第一主義的と称する自分第一主義を行おうとする動きがあります。まさに、世界の彼方此方で独裁的な首領を目指す政治家(と呼ぶべきかどうかわかりませんが)が、虎視眈々とその機会を狙っているような気がします。今回のアメリカ大統領選挙に感じる違和感は、その象徴かもしれません。 いずれにしても、日本においては国民による一つの判断が下されました。単に、政治と金というスキャンダルだけでなく、この国の将来や向かうべき方向性についての議論が聴きたかったところですが、政治もまた動いていくものです。これからも、誰がやっても同じなどといわず、多くの人が投票に行って欲しいと思います。本当に、今の世界情勢や身の回りの出来事等を通して、心からそう思います。 それは、長年の自治会活動や議員としての取組を通して、時を追う程私の中に深まっていく感情でもあります。まことに、民主主義というものは、ぼうっとしていると気が付いた時に、とんでもないことになっている可能性を孕んだ仕組みと言わざるを得ません。冗談ではなく、町内会長・区長というような地域の役職を決める時から、きちんとした人を選びちゃんとチェックしていく必要があります。 そのことは、本当に大切なことです。そして、もう一言いえば「頑張ってね」ではいけないといいうことです。私も、よくその言葉を耳にしますが、私も頑張る、或いは一緒に頑張りましょうでなければ、本当の民主主義は実現できないのではないでしょうか。
体育の日を過ぎ、ようやく秋らしくなってきました。一方、国会が解散され、大きな選挙を迎えています。さらに、知事選挙や地域の課題解決などの用事もありまして、多忙からは抜けきれません。 そうした日々の中では、多方面に渡って好奇心を張り巡らすことや、懐深く物事を捉える感性の余裕も失いがちです。ついつい、目の前のことに追われてしまいます。私自身、今は、ドジャースの大谷選手の活躍が心の支えのようなところがあります。昨日も、ナリーグ優勝決定戦の初戦に完勝し、今後の活躍が大いに期待されるところです。まことに、忙しい身には大谷頼みのような心情が伴います。 ところで、秋は私の一番好きな季節であります。例えば、日に日に深まりゆく秋の気配を肌で感じながら、つるべ落としに落ちてゆく夕日を惜しむ毎日は、まことに趣があるものです。その憂いのような感覚と並行して、或いはそれを慰めるように、秋の夜長を楽しむ相手をあれこれ考える一時も実に楽しいものです。とはいいつつ、この頃では諸事情によりそのような楽しみも随分減ってしまいました。 また、先ほど述べた選挙のようなものが無いにしても、この時期の行事は多く、少し顔を出すという程度の繰り返しでも、時間はあっというまに過ぎていきます。年々無理がきかなくなっていく身体を省みて、イメージ通りに動けないことに嘆息するばかりです。そのことは、秋の物憂さとは異なるものですが、いずれにしても人恋しくなるような心情に陥ることについて、否定する人は少ないでしょう。 やはり、そのような時に有難いと感じるのは、心通い合う仲間の存在というものです。そのことは、雑事の中でかわす何気ない一言などからも感じられるものです。例えば、そのような人たちとは、地域の諸行事や赴かなければならない場所において、しばらくぶりに顔を合わせたとしても、ほっとするような心の触れ合いを共有できるものです。私には、そのこと自体が有難いなぁと思う瞬間です。 他方、そうした「心通い合う」人達を自らが持つことについていえば、中々簡単なことではないかもしれません。やはり、どのような考え方にしろ、その生き方をぶれずに貫いて行くことが基本になるといえるでしょう。もちろん、政治的思想や本人が持つ価値観は夫々なので、お互いの生き方を受容し尊重できる人間性は不可欠ですが、一方で、あまり価値観が異なると共鳴し辛いのが人間でもあります。 私の場合についていえば、幸いにも、似たような価値観を共有しつつ情緒的な面からも相手を慮れるような友人知己に恵まれているように思います。そこには、本当に色々な立場の人がいて、しばしば顔を合わせる人から普段は中々会えないひとまで、たくさんの人がいます。それでも、私から見ると根底に流れる、人としての情愛や優しさを持っている人達ばかりだと思います。 そのような人達の価値規範について、簡単に述べれば日本人として持つべき精神性を備えている、或いは、日本人の精神性を理解しているということになるのだと思います。これからも、そのような人たちを大切にしていきたいと考えています。他方、そうした人間関係は短期間で構築されるものではありません。長い年月をかけ、色々なやり取りがあった結果得られる果実のようなものだと思います。 そう考えれば、それは、実は簡単に得られるものでもないといえるでしょう。一方で、先程長い時間がかかると述べましたが、それ程時間を要しない人もいるように思います。そのことについては、この頃感じることでもあります。何というのか、長い経験を通して私の中の物差しが精度を上げて来たといえるのかもしれません。実際、最初の頃調子が良いような人とは長続きしていないものです。 それを、言い方を変えて述べれば、私自身の中に価値観を共有できるかどうかを嗅ぎ分ける能力が高まったといえるでしょう。一方で、そうではなくて、単に辛抱が無くなった結果ともいえるかもしれません。いずれにしても、人が生きていく上において、心が通い合う友人知己を得られるかどうかは、大きな違いとなるように思います。しかも、その関係には弱者とか強者とかが無いことが重要です。 実は、このことは非常に大切です。良好な人間関係~と思っていても、意外と利益の共有やそれに付随する弱者・強者の関係が含まれていることはあります。元より、相手が強かろうが弱かろうが~というのが、長い年月をかけて私に培われた価値観だと考えています。例えば、具体的に言うと立場によらず相手を見極めるということだと思います。今後も、その姿勢だけは貫いていきたいと考えています。 柿の実が熟れ、民家の塀を超えて香りを運ぶ季節、そしてそれは金木犀のそれへと重なっていき、静かに秋は深まっていきます。移ろう季節の中で、田舎の祭りに心躍らされながらも、町でのお祭りに憧れて出かけていく~そんな少年時代は、ついこの前であったように思うのですが。
10月ですね。流石に、朝夕は涼しくなりました。このまま、私の好きな静かな秋が訪れてくれるのでしょうか。実生活は、月見の余韻に浸る間もなく、やらなければならないことが目白押しです。 そして、それ以外にも心を煩わされることはあります。例えば、ロシアによるウクライナ進攻によりロシア兵が7万人超、ウクライナ兵も3万人を超える死者数が報告されています。これに加えて、ウクライナの民間人犠牲者が1万人を超えているという話も聴きます。さらに、果てしなく続くイスラエルによるパレスチナ攻撃による犠牲者も4万人以上に上るとか、まことに暗澹たる気持ちになってしまいます。 よくマスコミなどでは、一人の命の尊さを訳知り顔で語られますが、戦争などで犠牲になった一人一人の命については、どのように考えているのでしょうか。淡々とデータを提供するように、犠牲になった人の人数が報告されるばかりです。しかし、その一人一人に人生があり、生きてきたドラマがあるはずです。さらには、生まれてすぐに理不尽な攻撃に晒されて、この世を去っていく命は尊くないのでしょうか。 他方、一人の命や人生という意味では、色々なことを考えさせられます。つい先日には、袴田事件の再審請求に関して、最高裁により袴田巌さんの無罪が言い渡されました。事件発生から58年の歳月を経て、無罪が確定(検察側が上告しなければ)したわけです。本当に、長い年月であったと思います。改めて、弟のために頑張り続けてこられたお姉さまに労いの言葉をおかけしたいと思います。 残念ながら、長い間の拘束による拘禁症を発症されたということで、本人は自身が無罪となったことさえよく解らないような映像をテレビで観ました。私は、その時この人の人生はどのようなものであったのだろうかと思いました。当然ながら、筆舌には尽くしがたい心労であったはずですが、私などが知る由もありません。一方で、今更無罪と言われても~というような思いが、私の心に浮かんできました。 確かに、無罪という判決を得て名誉は回復されたかもしれませんが、人生の多くの部分を刑務所で暮らさざるを得なかったこと(刑の執行に怯えながら)や、その間に手にすることができたはずの、人間としての幸福を味わう機会を失った損失は、どのようにしても埋め合わせできないものです。つまり、一度冤罪に巻き込まれてしまえば、それを受けた人は取り返しのつかない損失を被るということです。 このことは、冤罪事件ばかりでは無いと思います。例えば、北朝鮮による拉致被害者(家族も含めて)にとっても、同じようなことがいえるのではないでしょうか。私も、横田めぐみさんは生きていると思いますが、それを信じてひたすら待っている母早起江さんの心情を思うと、忸怩たる思いに駆られるのは私だけではないと思います。そして、この国はそんなことさえ解決できないのかと悲しくなります。 少し話がそれますが、敬虔なクリスチャンである早起江さんから熱心に洗礼を進められながら「本当に神がいるなら、こんな酷いことはしない」とそれを拒み続けられた横田滋さんの言葉が、改めて思い出されます。もちろん、人生は不条理で、世の中は理不尽なことばかりであることは、私も十分承知しているつもりです。それでも、魂の次元において、納得できない場面に出くわすことはよくあります。 そのうえで、よく考えてみると、私達はそうした「取り返しがつかない」人生を生きているのだと思います。実際、良いことも悪いことも含めて、一度起こったことは元には戻せません。元に戻したつもりでいても、時間が経過したことにより、そこには何らかの障がいや傷が残ることになります。所謂、取り返しがつかない問題が起きる訳です。単に、経済的な視点から見ても、大きな損害が発生することがあります。 例えば、ウクライナやガザ地区の復興のためには、途方もない予算が必要になるはずです。まことに、一人の人間(一人とは限りませんが)の間違った判断や邪な考え方が、多くの人々を苦しめる結果を招いてしまうことは、歴史の中にも明らかです。とはいいながら、人類がそのことを繰り返しながら綴ってきたのが、歴史というものであることも事実です。それもまた、取り返しがつかないものです。 歴史でいえば、勝者が歪曲し自らに都合の良いことを書くことは多々あります。しかしそれも、長い時間の経過が修正していくものでもあります。いずれにしても、過ぎたことは取り返すことはできない訳ですから、一人の人間のエゴにより多くの犠牲者や損害が出てはいけないことは当然のことです。さらにいえば、私達一人一人が、そうした取り返しのつかない人生を生きていることを自覚する必要があります。 一方で、私達は、子供の頃得られなかったもの(色々な意味で)や、本来なら手にすることができたはずのものに固執しがちになります。しかし、それも虚しいことなのかもしれません。少しでも、今生きている瞬間を大切にすることしか、できることが無いのだと思います(悟ることはできませんが)。
早、秋のお彼岸が目の前となりました。詳細は省きますが、雑事に追われて更新機会を逃してしまいました。とはいえ、その内容は、単に「雑事」では片づけられない責務を伴う時間ではありました。
さて、いつまでも暑い日が続く~が慣用句のように用いられる日々ですが、暦の上では中秋の名月(17日)を迎えています。そのようなこともあり、私の地元では久しぶりに観月会が行われました。地元自治会などが中心となり2019年9月に行われてから、気が付けば5年の月日が流れています。とても趣があり、有意義なイベントですが、2020年からのコロナ騒動がありしばらく中断しておりました。 地元の、まちづくり協議会や民生委員・愛育委員・健全育成会・消防団など、自治会組織を中心に集まった皆さんによる手作りの観月会です。さらにいえば、公民館活動の関係者や茶道の会の方々など、地元愛を行動の原動力とされるような人達に支えられたイベントでもあります。それにしても、前回から5年も時間が経ったことなど感じさせないような、地域の皆さんのぬくもりを感じました。 あえていえば、相変わらず顔を合わせるメンバーは同じような顔ぶれです。また、皆、夫々に年を取ってきたなぁとも感じます。何とか、後を担う人達の参加がもう少し増えればと思うのは、私ばかりではないと思いますが、これも中々解決する問題ではありません。一方で、奄美地方への台風接近など、空模様を気にしながらも観月会は無事開催されました。確か前回も、似たような天気だったと思います。 結果から述べれば、とてもアットホームで心地よい一時であったと思います。そうした雰囲気の中、私も、月に纏わるお話を少しさせていただきました。前回は、名古屋山三郎と出雲阿国を中心にした津山との関りなどを語りました。これには、山三郎のモデルの名古屋九エ門を祀った塚が私の家の裏の公園にあることを頼りに、ことある毎に山三郎の生まれ変わりである等と嘯く言い訳などもしました。 今回は、一月三舟と題して、月に纏わる三人の歴史上の人物が読んだ歌を並べ、お月見の夜の座興とさせていただきました。まず、一月三舟とは、本来仏教用語(仏語)でありまして、同じ月であっても停まっている舟から見れば止まって見え、北へ向かう舟かれみれば北へ動いているように見える。さらには、南に向かう舟から眺めれば、南に動いているように見えるという意味があります。 このことから、同じものを見ても、その人の立ち位置や置かれた環境によって印象も受け止め方も変わるのだということがいえ、物事は多様な視点から見て判断しなければならない~というような戒めがこめられているのだと思います。私は、お話の冒頭にこの言葉を置き、私の好きな阿倍仲麻呂、西行、そして光るの君へで今話題の藤原道長の詠んだ歌を三首挙げ、私なりの思いを説明しました。 実際、仲麻呂も西行も、小欄では何度か取り上げたと思います。特に、阿倍仲麻呂の溢れる才気と帰れなかった祖国への思いは、今の時代の人間には想像もできないような物凄いものであったのではないでしょうか。そのようなことは、西行についても同様にいえることだと思います。あの高杉晋作が自らを東行と称するほど心酔していたことをはじめ、男として強く心惹かれるものを備えた人物だと思います。 兎に角、今回の観月会では「私は、学者でも研究者でもありませんので」と前置きし、好きな人物やその人にまつわる歌などについて、思うところを語らせていただきました。そして、藤原道長の「この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば」の歌にもふれ、道長の人となりに関する一考も語らせていただきました。傍若無人や専横といったような、そんな人ではなかったのではというお話です。 実は、繊細な部分や他人の目を気にするようなところもあった人ではないかということや、この歌が詠まれた夜は望月(満月)ではなかたのではないか(十六夜)というお話など、近年の研究成果に基づくお話もしました。ただ、短い時間ですし話題提供といった趣でもありましたので、何点か言いたいことを言い忘れました。一方で、私の前には琴や詩吟の演奏があり、児島高徳を称える吟詠も聴けました。 全体を通して、コンパクトながらも和やかな風が流れる良い観月会であったと思います。これからも、地域の人達の手作りの営みによって、この和やかな風が流れ続けることを願います。私は、そのようなイベントや取り組みに関して、皆が力を出し合い継続していくことに大きな意義があると考えています。あらためて、人さえ良ければ~という言葉が頭をよぎりました。 ギラギラと光り輝き、生命の営みを支える太陽の強い力も必要ですが、夜の闇を得て美しく輝く月の光にも強く惹かれます。そのような思いは、日本人の精神性を備えた人にこそ、猶更強く感じられるのではないでしょうか。
8月最終週です。とはいえ、本当に暑い日が続きます。まだ、気配さえ感じられませんが、秋は私の一番好きな季節です。爽やかに流れる風の中、ゆったりとした時を過ごしたいと願います。 実際その通りで、結構忙しい日々を過ごしています。何というのか、やらなければならないことや、放っておけいないことをこなすだけで時間は過ぎてしまいます。一方で、もっとできた筈なのに~と思う身体の方は、どんどん無理がきかなくなっていく感じです。まぁ、それは当たり前のことなのですが、少し寂しい気持ちも湧いてきます。いずれにしても、まだまだやるべきことはたくさんあるようです。 さて、週刊誌(新潮)からの情報ですが、故立花隆氏の猫ビルが売りに出されているという記事を読みました。現在不動産業者が取得し、次なる購入者を探して売りに出しているという話でした。既に、10件以上の問い合わせがあるとも書かれていました。立花隆といえば、小欄でも何度も取り上げた知の巨人です。また、死生観に関する考え方など、私が強く影響を受けた人でもあります。 そもそも、亡くなった後は自らの遺体をごみと一緒に出せと言っていた位の人ですから、ものに執着しない人でしたが、猫ビルにあった5万冊を超える書籍は古書店に、段ボール100箱分の資料は知人の元に引き取られたということです。また、壁に描かれた猫の絵は、今ものそのまま残されているようです。亡くなられたのは、ついこの前のような気がしますが、早いもので既に3年の月日が経過しています。 改めて、人類の歴史の中で、知という媒体から恩恵を受け次世代に繋ぐという繋がりを持てたことに感謝したいという言葉が思い出されます。また、そのように思うことができれば救われるとも話しておられました。私には、そんなな立花さんの思いに対する理解が、時が経つほど深まってくるような気がします。 お盆で立ち止まって考えたことと合わせ、自らの生き方を振り返る時間でもありました。 他方、立花氏といえば、DNA以外で次世代に何かを伝えられるのが人間だという言葉があります。このことにも、大きく頷かされます。また、そうした考え方が例えば優秀な養子を迎えて家名や伝統を守ってきた、この国の文化に通じるものだとも思います。身近なところでは、津山藩の洋学や学問を支えた宇田川家・箕作家などが思い出されますが、数えきれないほどの事例があるはずです。 また、大工をはじめとする所謂職人の世界では、厳しい徒弟制度の中でものづくりの技が伝承されて来たのだと思います。それらのことも、DNA以外の方法による次世代への情報伝達の一環です。そもそも、膨大な書物や言い伝えなどの伝承により、人類は次世代の発展につながる情報を残してきたのだと思います。しかしながら、それらの膨大な文献や伝承も、人類の歴史の中ではほんの一部です。 例えば、多くの人に感動を与えるような文章や、輝くような芸術作品も、いま残されているものがすべてではありませんし、歴史の中で消えていったものの方が遥かに多いのかもしれません。とはいえ、文明という視点に立てば、それらの世代間を超えた情報伝達(DNA以外の手段による)が、今日の人類の反映をもたらしているということに違いはありません。 一方で、その根源にあるのは人類が持つ好奇心だと思いますが、ここで一つの問題が出てきます。元々は、ひ弱な哺乳類であった人類の脳には、今日までの発展を遂げていく過程において、地球そのもののキャパシティなどはインプットされていなかったのではないでしょうか。だからこそ人類は、自分たちの快楽や利便性を追求しながら、貪るように今日の文明を築き上げきたとも言えるでしょう。 結果的に、そのことが地球に過度の環境負荷を与え、人類そのものの生存や永続的な営みの可能性に疑問符を投げかけているのだと思います。そのようなこともあって、持続可能な発展などという言葉が用いられることになったのだとも思います。そこで、今日では良い好奇心と悪い好奇心を検証するような考え方もありますが、果たして本来の人類にそのような資質が備わっているのでしょうか。 他方、文化(カルチャー)という意味においては、カルトという言葉が示すように、宗教的なものが地球のキャパや限界を暗喩していたのだとは思います。誌面がありませんので、そのことは、またの機会に述べたいと思いますが、やはりことここに至っては、広義の意味での教育が極めて大切だと思います。そしてそこには、古来我々が培ってきた日本人の精神が据え置かれるべきだとも思います。 先日、岡山からの総裁候補と期待される人と膝を交え親しくお話する機会がありました。本当に高い資質と尊敬できる人柄を感じました。最後はそこに帰らなければならない~と、私が唱える日本人の精神性への回帰で意気投合していただきました。本当に、それは楽しい夜でもありました。
お盆が来ました。今年も、大切な人が先立っていきました。抗うことができない時の流れの中で、不条理や無常を感じながら生きて、それは充分理解しているつもりでも、仙人のような心持などにはなれません。それが、人というものなのでしょう。 本当に、暑い日が続いています。最近では、「外には出られんよ」という言葉が挨拶代わりに使われ、私も、親しい人との間で良く使います。実際に、今年の夏の暑さは、私がこれまでに体験してきた暑さとは次元が異なるものです。何か、人間の限界を超えたような感覚さえします。かつては、暑さに負けず頑張る~という表現がありましたが、今の暑さは、頑張ってはいけないという感じが強くします。 そのような中でも、パリオリンピックは予定通り開催されました。想定内や想定外など、様々な目論見違いなどもありますが、日本のメダル獲得数は海外大会において歴代最高であるという話も聴きます。個人的には、男女の卓球など、時差を超えてのテレビ視聴でかなり疲れました。また、ルールや判定の問題など、首を傾げることもありました。とはいえ、頑張った選手からはたくさん感動をもらいました。 一方で、そうした人間界のイベントとは関係なく、異常気象によるゲリラ豪雨等が彼方此方で発生しています。また、何か空恐ろしい気持ちを抱かせるように、南海・東南海地震の発生を思い起こさせるような地震が発生したりもしました。今日から明日にかけては、東北地方に太平洋側から台風が上陸するのではないかという、普段では考えられない予報が現実のものになろうとしています。 そのような状況の中ではありますが、今年も旧盆を迎えました。本来は、13日から夫々のお墓参りに赴くのが通常の流れだと思います。しかしながら私は、いつもの祖母のお墓にも早めにお参りしてきました。また、一連のお盆の行事もなるべくコンパクトに済ませるスケジュールにしています。理由としては、今まで良い加減に放っておかれた地域の取り決めを適正に執行することがあります。 詳細は省きますが、本来は田舎の農業用用排水施設に関する維持管理組合などは「まぁ、ええがな~」でやっていけるはずのものですが、だからこそ澱んでしまうこともあります。このことに関しても、たまたま私が指摘したために、正式な手順による執行を行う必要が生じ、その日程がお盆にかかってしまいました。本来は、私がいつも述べているように「人さえ良ければ」大事にせずともすむ話です。 他方、私は、前回も述べましたが先月末には、大切な友も失いました。そのことによる精神的な落ち込みが酷いことも、この暑さの中で強い倦怠感を抱える要因になっています。冒頭述べたように、人生の無常や不条理などは、本当にたくさん経験してきたはずですが、何物にも動じないような精神力の構築とか悟りを開いたような心境からは、却って遠ざかっていくような気さえしています(年と共に)。 それだからこそ、ほんの少しでも良いから時間を止めて考えてみたいと思うのです。例えば、私がここまで生きてきた中で、私の精神の成長を促してくれた人達や、暖かい恩情をいただいた人達のことなどについて、一人一人顔を思い浮かべながら考えたいと思います。実は、これまでもそうして過ごしていましたが、そのことが本来お盆にやるべきことなのではないかと、この頃さらに強く思います。 例えば、昨日は恩師の先生ご夫妻のご遺影に拝顔してまいりました。お忙しい中、ご親族の息子さんご夫婦が暖かく迎え入れてくださり、有難い一時を過ごさせていただきました。ただ、そのように墓所や仏壇に赴けるケースばかりではありません。エンジニアとしての師匠には、在りし日の姿を偲びながら有難い思い出を辿りつつ、お世話になったお礼などを心で語り掛ける一時を持ちます。 そのようにして、朝早く、或いは夜遅く、1人で机に向かいながらその人たちの顔を思い浮かべる時、何となく幸せな気持ちに包まれて行きます。上手くは言えませんが、癒されていくような感覚でしょうか。よく人は、幽霊が恐ろしいと言います。しかし私は、今述べたような人達であれば、幽霊であっても会いたいと願うタイプの人間です。本当に、もう一度会って親しく話したいなぁと思う人ばかりです。 その中に、今年は大切な友人が含まれてしまいました。遅かれ早かれ、そちらの世界があるならば、旧交を温めることは出来るのでしょう。しかしながら、今の私の心境は、そのような甘い連想を抱く状況でもありません。ただ、今は、目の前のこなさなければならない諸事情に没頭することにより、本来考えるべきことから目を逸らそうとしている状態かもしれません。ただ、生きているという感じでしょうか。 ともあれ、夏の一番暑い時期、少し立ち止まって人の世の無常などに思いを馳せるために、お盆という仕組みを作った先人達に敬意と感謝を捧げたいと思います。本当に、日本は良い国だと思います。
7月が終わります。今年の夏は、体温を超えるような暑さが続いています。なるべく外に出ず、目の前のことだけをこなしていますが、それでも草臥れてしまいます。無理は禁物です。 さて、いよいよパリオリンピックが始まりました。本当に魔物がいるようで、何が起きるかわからないのがオリンピックです。今回も、連覇がかかり、メダル獲得は当たり前とみられていた阿部詩選手が二回戦で敗退するなど、大きな波乱がありました。兄の一二三選手は、オリンピック二連覇を達成しましたが、試合に敗れ号泣する妹の姿を見ながらの戦いは、本当に辛いものがあったと思います。 そのオリンピックが開幕する頃、私は一人の親友を失いました。7月25日の正午頃のことでした。彼は、15年にも及ぶ長く厳しい闘病生活を終えて、旅だっていきました。27日の土曜日が通夜で、28日の日曜日の告別式となりました。私は、亡くなる何日か前に、彼から同級生による葬儀の実行を頼まれていました。そして、同級生の会(51会)の仲間達と一緒に大切な親友の弔いを行いました。 以前にも話したことがありますが、51会という会があります。これは、基本的には昭和51年に工業高校を卒業した者の集まりでした。今では、その範囲や定義は緩くなりましたが、本当に心が通い合う仲間の集いです。また、元々はゴルフの会でしたが、最近では飲み会や旅行にいくことの方が主題となってもいます。いずれにしても、その51会の中心に彼の営むお店があったことは事実です。 岡山の老舗で修業し、腕も材料も素晴らしかった彼の店は、本来は高級店というべきものでした(事実そうですが)が、私達同級生のためにいつも廉価で会場を提供してくれました。私達は、ことある毎にこのお店に集まり、日頃のストレスを発散し友情を温めていきました。本当に、我々のオアシスのような場所であったと思います。しかしながら、一代で築き上げた名店は主の逝去と共に閉店となりました。 このお店の主人で会った私の親友は、多少やんちゃな少年時代をこのまちで過ごし、岡山の有名店で和食の修行を積みました。何年かして、私たちが大人になった頃「あきが帰ってくる」という仲間からの知らせで、焼き肉屋に集まったことがありました。ガキ大将は少し大人になり「実力が勝負だ」と語り、私の建設現場での経験と重なる話を幾つもしてくれました。その時、どの道も同じなのだなぁと思いました。 また、お店に行くようになってからは、ネタを選ぶ目や腕の確かさになっとくさせられました。さらには、彼に高い美術的なセンスがあることも知りました。ではありますが、私にとっての彼は、拓郎の唄うアキラのような存在でもありました。まさに、かっこ悪いことが大嫌いで、自分に信念を持っていた男です。また、強いものにはどこまでも強く、一方で、弱い仲間を大切にする頼りになる男でもありました。 今、こうして、慌ただしく過ぎた葬儀を終えて、キーボードを叩いていると、たくさんの思い出が去来してきます。そして、そのBGMとして「いつまでも友達でいよう、大きくなっても親友でいよう。棕櫚の木の下を風が吹いている~」という拓郎の歌声が私の心に流れてきます。余談ですが、このアキラという曲は子どものためのものではなく、大人のために創った曲なんだなぁと改めて思います。 そんな私の友は、自分が重篤な病床にあっても、病を得た私のことをいつも心配してくれ、ことある毎に様子を聞いてくれる人でもありました。本当に、優しく頼りがいのある男でした。そんな彼を慕い、或いは頼りにして、お店を訪れる人が多かったのだと思います。「小さく」のはずが、多方面から生花が届けられ、大勢の弔問客が参列する通夜並びに告別式となってしまいました。 一方で、死んだ時は皆に会いたいから、小さくても良いので同級生で葬儀を取り仕切ってくれ~と頼まれた時の目は、少し潤んでいたように思います。また、祭壇のところから見ていると言った言葉が今も耳に残っています。人生は不条理です。信念を持ちひたすら生きている人間が、必ずしも報われるわけではありません。そのことは、百も承知ですし、理不尽や無常もたくさん体験してきました。 それでも、ため息をつくことがあります。この度のことも、そのうちの一つのように感じます。また、志半ばで亡くなる人や、こんな良い人が~と思う人の死に直面することもあります。私は、その度に色々なことを考えてきました。たくさんの書物も読んだつもりです。人生に意味はあるのかなどと力んだこともあります。人生に意味などないかもしれません。それでも、生きる(た)ことに意味はあるのだと思います。 ふと「死ぬまでは生きている」という立花隆の言葉を思い出しました。とりあえずは、目の前の課題に取り組む日々です。その中で、「生きていくことにとまどう時、夢に破れさすらう時、明日を照らす灯りが欲しい時、信じることをまた始める時、アキラがついているさ~」が流れ、親友の顔を思い浮かべるでしょう。
それは、梅雨明けの序章なのか、蒸し暑い日が続き、各地で豪雨被害の声が上がります。虚しい気持ちで、戦々恐々と空を見上げることさえあります。本当に、この頃の気象は荒っぽくなりました。 さて、海外からはトランプ元大統領の銃撃事件や、古江選手がLPGAメジャーのエビアン選手権に優勝した話など、ホットな話題が飛び込んでいます。まずは、地球そのものが小さくなったような実感がします。一方で、どうにもならない人類の愚かさを痛感せずに入られません。まことに、このキャパシティしかない星の上で、気に入らなければ殺してしまえ~というようなことで人類の未来があるのでしょうか。 そうしたエゴに基づく理由によって、独裁者の強権や基盤を維持するためにきわめて多くの人々が命を落とし、不安で厳しい生活を送っているのが現状です。だからこそという訳ではありませんが、本来の人情の機微というのか、人間同士の心の触れ合いを描いたドラマなどが見たくなることもあります。以前「時間ですよ」を再放送していたテレ東系で、現在は「ありがとう」の再放送をやっています。 地上波では、平日の午後4時前~5時前あたりでやっています。また、BSでも曜日を決めて2周分くらいを放映しているようです。私の記憶では、「ありがとう」は「時間ですよ」の少し前の頃だったと思いますが、当時圧倒的に人気があり非常に高い視聴率の番組でした。いずれも、山岡久乃さんと水前寺清子さんが母一人子一人の親子を演じる設定で、第一シリーズでは娘が婦人警官を志すお話です。 第二シリーズでは、家族体制で営まれる町の病院が舞台でした。父親がその病院の院長で、長男・次男が医師という設定です。そこを舞台に、付添婦として働く母親と看護婦(当時の名称はそれでした)として勤務する娘のやり取りを中心として、ドラマは描かれて行きます。また、病院に近いところにアパートがあり、婦長をはじめ病院の関係者が夫々に部屋を持ち、暮らしているという状況設定です。 例えばジェンダー問題とか、各種のハラスメントに関すること、そして現在のような厳しいポリティカルコレクトネスに制約される状況では、到底放送できないような内容の作品ですが、テレビ東京の英断(だと思います)に敬意を表したい気がします。ドラマの内容は、本当に小さな街の病院で起きる日常のエピソードから、人としてのあり方や思いの持ち方を問いかけるものであり、特別な話はありません。 基本的には、お互いに想い合っている二人が、未熟さや不器用さなどから中々上手くいかない状況を縦糸として、その周りに関係する人達の人間関係や夫々の思いが横糸となって織りなされるドラマといえるでしょう。ということですが、ざっくばらんな東京の下町気質というのか、そうした雰囲気が漂う作品でもあります。一方で、そのことは当時の時代背景や世相を良く反映したものになっています。 だから、私はこのドラマの中に、当時の日本人の価値観や精神性がうまく投影されていると思います。逆に言うと、それだからこそ50%を超えるような視聴率を獲得し、国民からの共感を得るという事実に結びついたのだと思います。そのことは、例えばポリコレに係るようなセリフが多用されていても、自分の内面への反省や相手の気持ちを慮るという、やり取りが随所にみられるところに現れています。 ところで、私には、今回改めて見ていて凄い発見がありました。それは、少しネタバレになりますが、かなり終盤において主人公の新(あらた→水前寺清子)と虎之介(石坂浩二)が結婚する場面の前後におけるシーンで、主要なドラマの登場人物である、近所の中華料理屋の三姉弟の長女のぞみ(大空真由美)が、天句践を空しゅうするなかれ~という児島高徳のエピソードに言及していたことです。 このことは、ドラマの本筋とは関係がなく、弟の万喜男(井上順)が姉にあてた手紙の中にあった一文を引用して語る設定です。しかしながら、かなり時間をかけ後醍醐天皇と児島高徳のエピソードを披歴したうえで、大空さんは「船坂山や杉坂と、御あと慕いて院庄~」いう児島高徳の歌をフルコース唄います。よほど、原作の平岩弓枝さんか石井ふく子さんに強い思い入れがあったのかなと感じています。 私も、1970年頃当時の放送を見ていたのだと思いますが、そのような記憶は残っていませんでした。今回、あらためてそのことを知り、心に響く感動のような気持ちを抱いています。そして、何ともいえない喜びのような感情も湧いてきました。今となっては、原作者やプロデューサーにその想いを確かめることはできないのだとは思いますが、どのような思いで挿入されたのか聴きたい気持ちは募ります。 実際、50年も前に作られたドラマです。世の中は随分変わってしまいました。それでも、人間の根底に流れる人情の機微に関しては、私の胸に伝わってくる部分がたくさんあります。実は、そこにこそ私たち日本人が持つべき精神性が内在されているはずです。今、少し懐かしく昭和を振り返っています。 |