これまでのコラムが納めてあります。
※バックナンバーはNO.1~NO55です。できれば、通してお読みください。
(根底に流れるものを、くみ取っていただけると思います)
![]()
![]()
![]()
![]()
これまでのコラムが納めてあります。
※バックナンバーはNO.1~NO55です。できれば、通してお読みください。
(根底に流れるものを、くみ取っていただけると思います)
2025正月の富士 烏城公園の貸ボート 夜桜(鶴山公園)
NO.55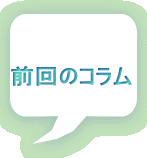
今週は、再び強い寒波が来襲するということです。そのような、記録的な降雪や寒さのために、人間社会に悪影響が出ませんようにと願う心も、人間中心の考え方というものなのでしょうか。 例えば、われ思うゆえにわれあり~デカルトや、パスカルの説く人間は考える葦である~というように、人間だけが物事を考える(考えられる)という立場に立てば、先ほど述べた「私達の社会に悪影響が出ませんように」と願う心は、所謂正しいものといえるでしょう。しかし、野生に暮らし、絶滅危惧種などと人から言われても、自らは何もできない動植物はどのように思っているのでしょうか。 そのように、哲学的に考えなくても、温暖化など地球環境の悪化が、あらゆる生命の生存に悪影響を及ぼすことは誰でも解るはずです。そして、地球を生命体を生存させ得る稀有な存在として考えれば、自国第一主義を標榜しながら自らの私服を肥やすような考え方が本来成立しないことが解るはず。しかしながら、どうも世の中の情勢はそうではない方向に突き進んでいるように思います。 それこそ、人類は自らだけが発明したお金という価値観だけを、すべての行動の規範とするようになってしまったのでしょうか。実際には、田舎で暮らし地域社会に溶け込み、人と人とのつながりを大切にして生きている人はたくさんいます。それは、都会の下町のコミュニティの中にも見かけられるものだと思います。つまり、何が言いたいかと言えば、問題は指導者とか上に立つ人間の考え方です。 その部分において、それこそ自分だけ良ければ良いと思う心が、独善的な振舞と反駁するものに対する容赦のなさを生み出しているのだと思います。そして、そのような心の持ち主同士の間では、こみあげてくるような情緒的な他者への思いやりなどを持つと、失脚という敗北を味わう羽目になることも多いはずです。そのことが、権力の中枢に行くほど他者への猜疑心を募らせることにつながるのだと思います。 先頃、紋別港の流氷初日が発表されましたが、私もその港に立ち、或いは流氷砕氷船に乗りその中を走る体験をしましたが、自然が織りなす営みの素晴らしさには感動という言葉しかありません。それは、2日後に初雪を迎える大雪の紅葉、何度も訪れてやっとみられる摩周ブルーの深淵な美しさなど、北海道だけでも枚挙の暇がありません。そのような場に立つ機会を得る程、地球の有難さを感じるはずです。 さらにいえば、そのような光景を眺めるだけではなく、しっかり見るということがとても大切なのではないでしょうか。そしてその効果は、今日のように映像技術が進歩した世界では、テレビや動画で見ても良いのですが、やはり本物を見ることが大切だと思います。例えば、その時の時刻や気温、或いは空模様、見ているシチュエーション(一人なのか複数なのか)等肌に感じられる条件でも違ってきます。 むしろ、置かれた状況により印象が変わるといった方が良いのかもしれません。また、先ほど述べた自然現象だけなく、建築物や芸術作品を含めた人工物においても同じとがいえると思います。例えば、日本には法隆寺をはじめとするたくさんの社寺仏閣があります。それは、海外においても同様です。実際に、万里の長城に立ってみなければ感じられないことがあるはずです。 さらにいえば、兵馬俑のように数体ではなく全体を見ることができれば、さらにイメージしやすく感動が膨らむものもあります。そのため(だけかどうかわかりませんが)に、地方のテレビ局の企画展から東博へと足を運び、遂には西安を訪れる程魅了されたこともあります。同時に訪れた始皇帝陵や大雁塔など、そこに立った時の感動は今でも忘れることはありません。 上手くいえませんが、やはり人間も動物の中の一つです。いくら理屈で考えても、理解できないことは出来ないし、一目見れば納得できる光景や事象があるはずです。さらに、本来動物である人間には自分でも解らない好みというものもあります。私が感動した吉備大臣入唐大臣絵巻は、他の人から見れば単に吉備真備を礼賛する絵画かもしれません。しかし、タッチや色遣いが美術書と違うことは解るはずです。 それを感じることが、夫々の感性だと思います。何の予備知識もいらないはずです。一方で私は、その感動を増幅させるものの一つとして、読書や体験を通して感じていたこと、その対象に対する予備知識があることが、実際に見た時の感動をさらに高めるのだと思います。実際に、二百三高地に立ち旅順港を見下ろせば、乃木・児玉のやり取りを含めた坂の上の雲の世界が、目の当たりに甦りました。 考えてみれば、そんな心象を持つのは人間だけかもしれません。一方で、その存在はこの広い大宇宙の中では極めて矮小なものでしかありません。さらに、宇宙の大きな営みの中では、人の一生など一瞬の長さもないでしょう。そうであればこそ、素直に感動し続けた人生が過ごしたいと思います。
まだまだ、災害的と言われる寒波は続いています。とても、、三寒四温という感じには程遠い気候です。その内、日本の四季は二季になってしまうのかと案じられます。 昨年後半あたりから、HPビルダーの調子が悪くなり(と言っても、素人が見よう見まねでつかっているので、次第にがたが来たような感じですが)表示がおかしくなったりして、ついには更新すらできない状況となっていました。またしても、友人のスーパーSE氏のお世話になることで、どうにか今キーボードをたたいています。有難いことです。 事程左様に、本来はきちんと理解して使わなければならないはずのものを、見よう見まねでやっているということはよくあります。というか、世の中の道具を使うというような行為についていえば、概ねそういうことになるのかもしれません。だれも、洗濯機や冷蔵庫の構造まで理解して使っている訳ではないはずです。もちろん、家電とPCは違います。 例えば、スマホなどでもそうですが、使うだけなら今どきの子どもの方が大人よりはるかに上手なはずです。とにかく触って、感覚で覚えるには若い方が有利だからです。一方で、ICT機器に接する際には、最初から道徳や倫理観が求められる場合があります。そこのところを、忘れずに教えて(ケアして)行く必要があります。 一方、幼少期などにおいては、素早く情報を受け入れる割に少しずれたりすることもあります。例えば、向田邦子のエッセイには「眠る盃」とか「夜中の薔薇」などというものがあります。これは、本来は「廻る盃」や「野中の薔薇」という歌詞のことなのですが、幼少期に耳から入った言葉をそのように勘違いして記憶していたというものです。 私もずいぶん大きくなるまで、「おうえん川」という名前の川があるのだと信じていました。これは、母さんお肩をたたきましょと唄いだす曲の詞ですが実際には「お縁側」です。そればかりか、巨人の星(これも古いですが)の星飛雄馬は、自然の道(本来は試練の道)をゆくという風に歌っている同級生などはたくさんいたように思います。 その程度なら可愛いものなのですが、本来の語彙を云々という話では正確な言葉遣いが必要になります。いつでしたか、ローマ教皇の話題になった時に軽い気持ちでローマ法王と私が口にしたことについて、すかさず「教皇だろ」と指摘されたことがあります。私にすればローマが一神教となり、皇帝に冠を授ける立場になった時から呼び名はどうでも良いのです しかしながら、ニュースなどを見ながらの会話(雑談でしたが)などにおいては、そんな私の心の内面などは関係ないことなので、教皇というべきだったのかなぁとおもいますが、何となくもやっとした感覚は残りました。同じ日本人同士でもそうなのですから、使用言語が違う相手と微妙な交渉を行う際などは本当に大変だろうなぁと思います。 そのうえで、話し言葉を文書として残す場合も考えられます。そのようなことを考えればなおさらです。考えてみれば、そもそも自分自身のことがよく解らないのに、他者と解り合うなどということは、本当に大変なことだと思います。とはいえ、前出の向田邦子には阿吽という作品もあります。あえて言葉にせずとも、充分解り合えることもあるはずです。 さらには、あえて言葉にしないほうが上手くいくということさえあります。むしろ、日常生活においては、その阿吽の呼吸というやつで通じ合っていることが多いように思います。またそれは、親子・夫婦というように関係性が近くなるほど成立するように思います。何か悩みがあるのか、問題があるのかということなどは自然と伝わるものです。 かつての地域社会は、関係性が今よりも近く濃いものでした。さらには、仕事場などにおいても同様でした。それが、今日の我が国の社会では、人同士の関係性が遠く薄いものとなり続けています。上手く言えませんが、地域力が脆弱化し続ける要因は、そこにあるのだと思います。地域社会では、大人と子供が深く関わり合いながら暮らすことが大切です。 一方で、人間同士の距離が縮まれば、傷つく度合いも高まりエネルギーもそれだけ必要です。それは、本来当然のことなのですが、バイト探しの〇〇とか退職代行などが繁盛するように、私達は、自ら人との関りを希薄にしてきたわけです。その辺から、考える必要もあるのだと思います。
大寒を迎えました。一年で一番寒くなる時期と言われています。個人的には、次の立春辺りが一番寒いような気もします。そういえば、初めて流氷を見に行ったのはその頃でした。 さて、海の向こうでは自国第一主義を標榜しながら、巧みに資産形成を図る人がいよいよ大統領に就任するようです。近隣の覇権主義の国と対峙し続ける我が国においては、戦々恐々としてその様子を見守る~といった感じなのでしょうか。一つの便りとすべき隣国における大統領の命運と共に、気になるところではあります。 一方、元日から3週間くらい過ぎていても、今年になって初めて会う人と「おめでとうございます」という挨拶を交わす日常が続いています。日本語は、挨拶の言葉だといわれます(愛を語るフランス語的に)が、そこには言語の響きだけでなく、日本人の精神性やそこから派生した礼儀正しさが投影されているのだと思います。 まだまだ今月中は、冒頭のあいさつにその言葉を誰かが使う会合が続くでしょう。私も、極力その数を減らしながら挨拶を交わす日々を続けているのが現状です。まぁ、形骸化しているものや、本当に必要なのかというような儀礼的なものもありますから、先ほど述べたように取捨選択をしながらということにはなります。 実際、人間同士としてのコミュニュケーションは、相対してみなければ解らないことや伝わらないことがたくさんあります。「この人も老けたなぁ」などと、自身の経年劣化を棚に上げた感慨を持つこともよくあります。また、いつもと同じような話題に終始したとしても、不思議と癒される相手はいるものです。 やっぱり、そこには、息遣いが伝わるような距離で話して見ないと解らない何かがあるのだと思います。上手くは言えませんが、その場が持つ空気感や相手と自分との関係性により醸し出されるものの違いでしょうか。もちろんそれは「感」ですから、夫々の感じ方によって感じ方が異なるのは当然です。 とはいうものの、この頃私が思うことは、そのように感じる私の感覚の物差しが「あれっ」という感じでずれることが多くなったようなことです。さらにいえば、その場に漂う空気に馴染めない場面も増えたように思います。そこに、私自身の老化と社会状況の変化があることは否定しませんが、一抹の寂しさもあります。 そもそも私は、そこまで言わなくても~というような感覚の人間です。したがって、、そこまで言わなければ解りませんか~というようなことは、本来はいいたくありません。しかしながら、これまでの人生を振り返ってみると、皆が息をのむような微妙な雰囲気の時に、そのことを言い切る役割を果たしてきたように思います。 特に、自治会活動等に積極的に取り組むようになってからは、そうした場面が多くなったように思います。もちろん、多くの場面において止むにやまれぬ思いで皆のために「正義を通して」きたつもりです。しかし振り返ってみれば、その熱い思い程には、程感謝されている訳でも無いような感じさえ受けます。 実際には、見識ある多くの人から有難い評価とご理解を得ていることも承知しています。それでも、「お前が頑張れ」的な空気を払拭し、笛吹けど踊らぬ人々を躍らせるほどの力を発揮できたという自負が持てないことも事実です。結果的に、私が理想とする地域のあり方から遠ざかっていく様子を傍観している気分です。 ここまで、簡単に空気という表現をしてきましたが、私は、それはとても大切なものだと考えています。それは、しっかりとした地域があり、あえて言葉にしなくても~という理念や気概を備えた大人たちが、伝統文化を守りながら子育てをしていく中において育まれ継承されていくものだと思うからです。 その部分に、もう少しきっちりコミットしたかったなぁと思うのが、この頃の心境です。ただそこには、時代の流れやタイミング等様々な不確定要素がありますので、今現在において評価したりされるべきものでもないのだと考えています。
あけましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。 何というか、今年は私にとっては比較的穏やかなお正月だったと思います。そこには、私が行動する範囲の気象状況がそうでしたし、年末年始の行事への参加を少しセーブしたことにも一因があるかと思います。と言っても、それ程東奔西走している訳ではないので、まぁ、例年と変わらない年末年始だったかなと思います。 もちろん、恒例の箱根駅伝も見ることができましたし、その合間をくぐって大学ラグビーの準決勝も見ることができました。駅伝では、青山学院が往路でトップに立ち、総合優勝しました。一方、私が「推している」中央大学は、熱い走りを往路で見せてくれました。結果的に、往路では2位、総合でも5位でシード権獲得を果しました。 他方、ラグビーの方では明治に帝京が勝ち、京産大に早稲田が勝つという結果になりましたが、どちらも質の高い良いゲームであったと思います。何よりも、日本のラグビーのレベルは格段に進歩していると思います。それは、新日鉄釜石や神戸製鋼が連覇を重ねていた頃と比べても、そのように思います。 またぞろですが、その神戸製鋼の連覇の立役者である、平尾誠二の言葉が思い出されます。積極的に海外の選手を受け入れ、強い相手と渡り合いながら(先ずは、胸を借りながらでしたが)日本のラグビーのレベルはは確実に上がっていきました。このことは、箱根駅伝を見ても考えさせられることでもありました。 まだ、完全に外国人が自由に何人でも走れるようではないですが、強い留学生を受け入れ切磋琢磨してきた中で見られる成果もありました。例えば、今年の花の2区では、東京国際大学のエティーリ選手が区間新記録更新しましたが、同時に、2人の日本人選手(創価の吉田・青学の黒田)も区間記録を出しています。 この区間では、9位までに外国人選手はエティーリ選手だけで、残りは日本人選手が上位を占めています。やはり、全体のレベルが向上しているのだと思います。まぁ、箱根に関していえば、人気に伴う予選会参加校の増加などもレベル向上の要因ではありますが、力のある外国人選手を受け入れて来た成果はあると思います。 話は変わりますが、民主主義政体の中においてもそうした取り組みをしていくために、議論を重ねながら適正なるウールづくりをしていくことが重要です。もちろん、完璧というものはないかもしれませんが、胸襟を開き多様な方面から真摯な議論をしていくことが大切です。それに基づき、公正な決定をしていく必要があります。 前回も述べましたが、政局になることを求めて批判を繰り返すだけでは、そもそもお話になりません。例えば、対案を掲げ、自分なら(或いは自分達なら)こうした将来像を描くという提案を示し、その実現性を裏付け具現化するための手法について論戦を張りあいながら、議論の質を高めつつ方向性を探るようなことです。 またその検定には、夫々が基本とし寄り心とする明確な政治方針があるべきです。その上で、欲望の資本主義といわれる資本主義の再検証や、限りある地球で今後人類が向かうべき方向性を抽出するための質の高い議論が必要です。いずれにしても、行き過ぎたポピュリズムや誹謗中傷合戦は民主主義の敵だと思います。 私は、そのためには政治家を選ぶがワン責任もあるのだと思います。これもいつも述べていることですが、ほんの小さなところから「民主主義」を考えたうえで行動していくことが大切です。何よりも、今は未だそれが許されているのですから。
今年も、あと一週間です。体感的に日一日と過ぎる時間はもの凄く速く感じますが、つい一年前のことを随分昔のことのように思ったりします。それが、年を取るということなのかもしれません。
さて昨日は、年末恒例のスポーツ行事である全国高校駅伝が行われました。男子は佐久長聖、女子は長野東という長野県勢が優勝するという結果となりました。特に、男子は最後まで行方が分からない展開で、佐久長聖が大牟田を振り切る結果になりました。また、女子も長野東が終始先頭を走る展開でしたが、圧倒的という感じではなく選手全員による総合力を感じました。 何よりも、男子の一区を走った、千葉八千代松陰高校の鈴木琉胤選手の走りは圧巻でした。それまでの区間記録を破る28分43秒をマークしました。特に彼は「先輩の記録を破る」と公言し、見事それを実現しました。非常に大きなプレッシャーであったと思いますが、何か堂々と成し遂げたという印象さえ持ちました。今後に期待したいところです。 一方で、外国人選手を主要な区間で起用してはいけないというルールにより、好成績が得られない学校もありました。男子では、岡山県の倉敷高校が10年連続の入賞(8位以内)をのがす結果となりました。反面、外国人選手が出てきた区間では、それまでの区間記録を何人もの選手が更新する場面も見られました。簡単に言えば、日本人選手とはけた違いのパワー見た印象です。 ルールについては、色々な議論を重ねて決められたことだと思いますので、素人が文句を言う筋合いではないと思います。しかしながら、大学駅伝でもそうでしたが、この「外人枠」の扱いに関しては、すっきりする場面が少ないように思います。私は、その競技がグローバルなものとして認知され、幅広く人気を得ようとするのなら、なるべく開かれた形のものでなければならないと思います。 一方で、一本の襷をつなぎ皆で勝利を目指す駅伝のような競技は、極めて日本人の情緒感に馴染む協議でもあります。そうした背景があり、外国人の快走を快く思わない感情が湧く人もいるのだと思います。この他、日本人選手の実力向上のために、先ずは日本人選手で闘わせるべきであるという考え方もあるでしょう。しかしどうでしょうか、サッカー、ラグビー、野球…それで強くなった協議はありません。 もちろん、直接走り・跳ぶというような競技は、球技等に比べて技術で対応することが難しいといえるのだと思いますが、かつて平尾誠二が言っていたように純血主義に拘っていたら強くはなれないという言葉が思い出されます。今後、時代の変化や日本人の体力・体質の変化なども予想されますからどのように変わっていくのか解りませんが、様々な思いがよぎった年末の風物詩の感想です。 ところで、公正なルールに基づく公正な競争ということからいえば、民主主義しゃかいにおける選挙のようなものが考えられます。しかし私は、ここ数年続く国際社会の情勢や、この国で行われている選挙の様子等を見ていて、随分と違和感や虚しさを感じることが多くなりました。このことも、最近よく述べていることですが、努力しても追いつけないような格差社会は拡大し続けています。 そのことが、目先の苦境を解決(それも一時的ですが)してくれそうな強者へ、依存しようとする感情を高めることにつながります。例えば、アメリカの移民がそうであるように、既にアメリカに住む人は新しい移民を拒み、これからアメリカに入りたい人は寛容な政策を求めるという具合です。そうした、僅かな既得権のために絶対的な権力者を求めるような風潮は極めて危険な考え方だと思います。 しかしながら、現状が厳しい人々は、そうした解りやすい独裁者を選びがちです。現在の自国第一主義的といえる世界情勢は、そこに依拠しているともいえます。結果的に、公正なはずの選挙が公正に行われなくなり、嘘であれなんであれ強く愛艇を誹謗・中傷しても、人気を得たものが勝者となる傾向が高まっています。その手法ややり方については、誌面の関係で言及しませんが残念です。 そのことに大きく影響し、存在感を示すのがSNSというものだと思います。その影響力は、圧倒的に進歩するIT技術の進化と共に、どんどん大きくなっています。またそうした傾向は、小さな地方都市でも容易に見ることができます。一人何役もこなし、議論を先導しようとしたり、ただ政局になりさえすればよいという目的で、ターゲットを攻撃する輩やその動きは年々強くなっています。このことも、残念なことです。 とりあえず、目先の相手にダメージを与えれば良いという考え方の人達に、地域住民や市民のために何ができるのかと考えれば、よく解るはずです。まずは、世の中を良く見て何が正しいのか(信ずるに足りるのか)を、しっかり吟味していくことが必要であり、大切なことだと思います。
そうですね。いつの間にか私自身が年を重ねている訳です。実は、私達はそのことに気づかないまま(気づかないふりをして)、日々を重ねているのだと思います。令和6年も終わろうとしていますが、平成の30年間は何をしていたのだろう~などと考えたりします。それこそ、多忙な日々に追われながらあっという間に駆け抜けた年月であったのだと、改めて振り返る自分を見ることができます。 実際、私の青壮年期は昭和後期から平成の世でした。また、技術士の資格を得た西暦2000年は平成12年です。それ以降は、それまでの「世の中の役に立つものづくり」という思いに加え、原点にあるべき「日本人の精神性」の大切さへの思いが深まりました。小欄での発信は、そのような思いが原点となっています。もちろん、中には私自身の愚痴や、時折〃の心の動きが投影されています。 そして今、暮行く令和6年の師走に思うことは、昭和という時代への郷愁とその時代に生を受けたことに対する感謝のような気持ちです。昭和といっても、私の生きた30年代以降と戦前戦後を含めたそれ以前では、まったく内容が違います。父や母の世代のように、あの悲惨な戦争を直に体験した時代や、「戦争を知らない子どもたち」を唄っていた前代とも私の生きた時代は異なります。 理由はどうであれ、圧倒的な高度経済成長の時代に育った私達には、幼少期と青年期を比べても比較にならないような物質的な豊かさがもたらされました。そうした、目まぐるしく変化していく社会情勢の中で、所謂頭でっかちの少年達は、先ずは戦争を知らない子どもたち世代の人々のカルチャーや音楽に強く影響されました。反面、戦前から続く厳格な父親世代の強烈な躾も受容して育ちました。 中々上手く言えませんが、私達は、敗戦をきっかけに大きく変わった世の中の論調や教育というものの、双方を体感しながら育った世代だといえるでしょう。例えば、私達は祖父や父の世代から聴く戦時の体験や苦労話を、自らが体験したようにリアルに思い浮かべることができるはずです。一方で、学生が世の中を変えるのでは~という空気を肌感覚で感じられた少年時代も過ごしました。 このような言い方が良いのかどうかわかりませんが、私達は、まことに恵まれた時代を生きて来たのではないかと思います。もちろん、細かくいえばオイルショックの影響をもろに受けたとか、高度経済成長の終焉の中でもがいたというような負の部分もあると思います。それでも、この国においては、手に職を付ければ(技術を身に付ければ)それなりに生きていける実感が感じられた時代でした。 何よりも、多くの人が世の中のことを考えていた時代でもあったと思います。さらにいえば、胸に手を当ててものを考え、お天道様に恥ずかしいようなことはしない~というようなことを、改めて口にしなくても誰もが(多くの人が)わきまえていた時代であったと思います。もう少しいえば、私のように身勝手に生きて来た人間が世に問うような形で、小欄のような発信をすることがおこがましい時代でもありました。 かくいう小欄も、2002年から綴っておりますので、22年の歳月が流れたことになります。鳴らし続ける警鐘に逆らうように、世の中の流れは私の思いとは違う方向に進んでいます。もちろん、そのような世の中に対する危機感やある種の使命感のようなものは衰えていないつもりですが、虚しい気分に浸る機会も多くなりました。とりあえずは、できることをできるだけ~というような感じでしょうか。 ともあれ、何をどう言おうと、人は生まれる場所も時も選ぶことは出来ません。与えられた場所と時代の中で、もがいていくのが人生ということだと思います。しかしながら、どうやら戦場に赴くことも無く、心ならずも他者の命を奪うこともせずに生涯を終えられるのだろうと思いますし、多少なりともバブルが崩壊するまでのお祭り騒ぎの片鱗のおこぼれに預かることもあったと思います。 また、デジタルではなく、アナログな形の書物に多く触れることもできました。そのことが、私の幼少期を形作っているといっても過言ではありません。そして、それは現在の私を支える根幹でもあります。そのような意味からも、私は、恵まれた時代を生きさせてもらったのだと思います。ただ今は、中村草田男の「降る雪や明治は遠くなりにけり」の句の明治を昭和に変えたい気分です。 一方、生老病死には抗えませんが今年も私の好きな人たちが先立ちました。身近では大切な親友が逝きました。ミーハーなファンとして日野正平さん・北の富士さん・西田敏行さん等の芸能人、さらには血と骨の簗石日氏・小澤征爾氏・札幌のヒーロー笠谷幸生氏…考えてみれば昭和の思い出ばかりです。 |